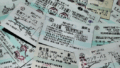秋になると話題にのぼる「松茸」。日本の秋の味覚の代表格として、香りの良さが特に称賛されていますよね。その芳醇な香りを楽しみにしている方も多い一方で、実は「ちょっと苦手…」「正直、くさいと感じてしまう…」という声も少なくありません。
この記事では、そんな松茸の香りに対する感じ方の違いや、「なぜくさいと感じてしまう人がいるのか?」という疑問を、やさしい口調で丁寧にひもといていきます。香りの成分や文化的背景などにも触れながら、苦手に思っている方にも安心して読んでもらえるような内容にしています。
「好き」「苦手」に関わらず、松茸の香りについて新しい発見があるかもしれません。どうぞ最後までゆっくりご覧ください。
松茸が「くさい」と感じる人は意外と多い?

SNS・口コミに見る“くさい派”のリアルな声
実は、「松茸がくさい」と感じている人は思ったより多いようです。SNSやレビューサイトには、
- 「お線香みたいなにおいがして無理だった」
- 「香りが強すぎて気分が悪くなった」
- 「土のようなにおいが鼻について、食べられなかった」
といった声が寄せられており、決して少数派ではない印象です。中には、毎年話題になるたびに「自分だけが苦手で恥ずかしい」と感じていたという意見も見られます。
「お線香みたい」「カビっぽい」などネガティブな感想
具体的な表現としては「お線香のよう」「カビ臭い」「湿った落ち葉のにおい」などが多く見られます。
また、
- 「風通しの悪い古民家のようなにおい」
- 「山に入ったときの湿気の強い空気」
といった比喩もありました。どうやら“土っぽさ”や“渋み”のある香りに敏感に反応してしまう人が多いようです。
中には、松茸そのものよりも「調理したときに部屋にこもる匂いが苦手」という声もあり、単なる味覚ではなく空間の印象まで影響することがうかがえます。
嗅覚が鋭い人ほど苦手に感じやすい傾向も
香りに敏感な方、特に香水やアロマに弱いタイプの人は、松茸の香りにも強く反応してしまうことがあるようです。たとえば、香水売り場や洗剤コーナーで頭痛がするようなタイプの方は、松茸の香りを「強烈で不快」と感じることが多い傾向があります。
また、嗅覚が研ぎ澄まされている方は香りの微細な成分まで拾いやすいため、松茸のように複雑で濃厚な香りは「情報量が多すぎて疲れる」といった印象を持つこともあるようです。
さらに、過去の経験や記憶と香りが結びついている場合、たとえば不快な思い出と関連づいた香りは、より強く苦手意識として残ることもあります。
松茸の香りの正体は?苦手と感じる科学的な理由

「マツタケオール」ってどんな成分?
松茸特有の香りの正体は「マツタケオール」という成分。この芳香成分は、松茸が他のきのことは異なる“特別な香り”として知られる理由でもあります。 マツタケオールはごく微量でも非常に強い香りを放つのが特徴で、鼻にツンとくるような独特の風味があります。
さらに、この成分は揮発性が高く、加熱されることで香りが一気に広がる性質を持っており、調理方法によって香りの印象が大きく変わることもあるのです。また、自然界では松茸以外にはほとんど存在しないとされており、希少性の高い香りとしても注目されています。
良い匂いと悪臭は紙一重?香りの感じ方の仕組み
実は香りの“良い”“悪い”は、個人の体験や記憶、文化的背景によって左右されます。例えば、幼少期に松茸の香りと楽しい思い出が結びついていれば好印象を持ちやすいですし、逆に風邪をひいたときの食事と関連づいてしまうと、苦手意識が芽生えることも。
また、ある文化圏では好まれる香りが、別の地域では“くさい”とされることも珍しくありません。嗅覚は感情や記憶と強く結びついているため、香りの印象は驚くほど主観的なものなのです。
香水や柔軟剤と似た“芳香族化合物”の特徴
マツタケオールは、香水や柔軟剤に使われる芳香族化合物と同じような性質を持っています。これらの成分は、香りの持続力があり、空間に広がりやすいという特徴があります。そのため、松茸の香りも「部屋全体に充満してしまう」「衣類に残るほど」といった印象を与えることがあります。
このような強い香りは、リラックスや高揚感を与える一方で、刺激が強すぎると感じる人にとっては頭痛や吐き気の原因にもなり得ます。結果として、マツタケオールが持つ濃厚で芳醇な香りは、人によっては「高級感」ではなく「重たさ」や「不快感」として受け取られてしまうこともあるのです。
日本では高評価なのに、海外では不評なことも?

松茸は“日本限定のごちそう”?
日本では秋の風物詩として、松茸は特別な存在です。料亭のコース料理や贈答品にも使われ、その香りは“高級感の象徴”として親しまれています。しかし、海外、特に欧米や中国以外のアジア地域では「においが独特すぎる」「味に見合わない」として、あまり歓迎されないことも。
アメリカでは、松茸を食べる文化自体が一般的ではなく、その独特の香りを「湿った木材のよう」「古い倉庫のにおい」と表現する声も見られます。こうした反応は、松茸が持つ香りの個性が普遍的ではないことを示しています。
文化が香りの好みに影響する理由
私たちが“良い香り”と感じるものには、育ってきた文化や習慣が大きく関係しています。たとえば、日本ではだしや発酵食品に代表される「旨み」を含んだ香りが好まれがちで、松茸のような深みのある土壌系の香りも受け入れられやすい傾向があります。
一方、欧米諸国ではハーブやバターのような軽やかで華やかな香りを好む傾向があり、松茸のような“重みのある香り”は「重苦しい」と感じられることも。その結果、「おいしそう」と「においがキツい」は文化によって分かれるのです。
また、香りに関する教育や慣れも大きな要素であり、日常的に松茸に触れる文化では“なじみ深さ”から好印象を持ちやすいという側面もあります。
「高級=ありがたい」という思い込みも影響?
高価なもの=おいしい、ありがたいと感じる心理は、多くの人に共通するものです。松茸は価格が高く、収穫量も限られているため、「手に入れるだけで価値がある」というイメージが定着しています。そのため、実際の香りがどうであれ、「高級な香り」と認識されやすくなるのです。
このような価値観は、香りそのものに対する評価に大きく影響します。「高級なものだから好き」と感じる人もいれば、「値段の割にくさく感じてしまった」とギャップを覚える人も。松茸の香りに対する意見が二極化する背景には、こうした心理的なフィルターがあるのかもしれません。
松茸の香りが好きな人の理由とは

秋の訪れを感じさせる“季節感”の演出
「松茸の香り=秋のにおい」と感じる方も多く、季節感を楽しむ手段として愛されています。特に、肌寒くなってくる時期に漂う松茸の香りは、秋の深まりを実感させてくれる存在。紅葉や栗、さつまいもなどと並ぶ“秋の風物詩”として、食卓に季節の彩りを添えてくれます。
さらに、秋の行楽や家族での食事会など、松茸の登場は特別な時間を演出するきっかけにもなります。料理を通して季節の移ろいを感じることは、心の豊かさにもつながりますね。
高級食材ゆえの“特別感”がプラスに
「一年に一度の贅沢」としての特別な体験が、香りをポジティブに変えているともいえます。なかなか手に入らない食材だからこそ、味わえること自体が「幸せな出来事」として記憶に残ることも。
また、お祝いの席や贈り物など、松茸が登場するシーンは“非日常”を感じさせてくれます。そのときの雰囲気や想い出が香りと結びつき、「松茸=いい香り」という印象を強くしているのかもしれません。
子どもの頃苦手だったけど大人になると好きになるケースも
味覚や嗅覚は年齢とともに変わることもあります。子どもの頃は「変なにおい」と感じていた香りが、大人になると「深みのある香り」として受け取れるようになるケースは少なくありません。
特に、苦みや渋み、香ばしさなどの“複雑な味わい”は、経験を重ねる中で徐々に魅力として感じられるようになる傾向があります。松茸の香りも、その一部といえるでしょう。
「昔は苦手だったけれど、久しぶりに食べたらおいしかった」という再発見も、大人の味覚の楽しみのひとつです。
食べ方で印象が変わる?松茸の香りを楽しむコツ

香りを引き立てる料理例(焼き松茸、土瓶蒸しなど)
焼き松茸や土瓶蒸しなどは、松茸の香りをダイレクトに感じられる料理として有名です。特に焼き松茸は、炭火やグリルで香ばしく焼くことで香りが引き立ち、素材本来の魅力を味わえます。土瓶蒸しは、香りが閉じ込められた状態で提供されるため、ふたを開けた瞬間の香りの立ち上がりを楽しむことができます。
また、焼き松茸には少量のすだちを添えることで、香りに爽やかさが加わり、さらに引き立ちます。こうした料理は、松茸の香りを存分に堪能したい方におすすめです。
初心者におすすめなのは「炊き込みご飯」や「すまし汁」
松茸が初めての方には、炊き込みご飯やすまし汁のように、香りがやさしく広がるメニューがおすすめです。炊き込みご飯では、だしと一緒に炊き込むことで香りが全体にほどよく移り、苦手な方にも受け入れられやすくなります。
すまし汁にすると、透明感のある味わいの中に松茸の香りが上品に漂い、強すぎると感じにくくなります。さらに、他の具材と組み合わせることで香りがやわらぎ、食べやすくなるのもポイントです。
苦手な人向けの調理アイデアと香りの和らげ方
香りが強すぎて苦手という方には、少し工夫をすることで松茸を楽しめる可能性があります。たとえば、レモンやすだちを軽く絞ると、香りに柑橘系の爽やかさが加わり、重たさが和らぎます。
また、だしをしっかり効かせたり、しょうゆやみりんなどの調味料をやや強めにすることで、松茸の香りが全体の中にほどよくなじみます。オーブンやフライパンで香ばしく焼くのも、苦手な香りをやや抑えるのに有効です。
「少量を味見してみる」「他の具材と一緒に食べる」など、少しずつ慣れていくのも一つの方法です。無理せず、自分に合った食べ方を見つけていきましょう。
「松茸が苦手」は変じゃない!

味覚も嗅覚も人それぞれ。無理に好きにならなくて大丈夫
「苦手=おかしい」ではありません。人によって味や香りの感じ方はまったく異なります。たとえば甘いものが好きな人もいれば、しょっぱいものが好みの人もいますよね。それと同じで、松茸の香りを「いい香り」と感じる人もいれば「くさい」と感じる人がいるのは自然なことです。
また、体調やその日の気分によっても香りの印象は変わることがあります。「今日はちょっときつく感じるな…」という時があっても、それはおかしなことではないんです。無理して好きになる必要はまったくありません。
他のキノコで秋の味覚を楽しむ方法も
松茸の香りが苦手でも、秋のきのこを楽しむ方法はたくさんあります。たとえば、しめじや舞茸、エリンギなどは香りがやさしく、食感も豊か。料理に取り入れやすく、さまざまなレシピに合う万能食材です。
最近では、香りを抑えた「松茸風味調味料」や「松茸ごはんの素」なども市販されており、ほんのり松茸気分を楽しみたい人にもぴったり。無理せず自分に合った方法で、秋の味覚を楽しんでみてくださいね。
「苦手」はあなただけの感性。否定せず受け入れて
香りや味の好みは、その人だけが持つ“感性”です。誰かと違っていても、それはあなたらしさのひとつ。たとえば、みんなが「おいしい」と言っていても、自分には合わないと感じることってありますよね。
その感覚を否定せず、「私はこれが好き」「これはちょっと苦手」と素直に受け入れることが、食の楽しさにつながります。大切なのは、自分の気持ちに寄り添って無理せず楽しむことです。
まとめ|松茸の香りが苦手でも、あなたの感じ方は正しい
松茸の香りを「くさい」と感じても、それはあなたの正直な感覚です。誰かと違っていたとしても、それは決しておかしいことではありません。私たちはそれぞれ異なる経験や嗅覚の持ち主であり、感じ方に正解・不正解は存在しないのです。
大切なのは、自分の味覚や嗅覚に素直になり、無理をして迎合せず、自然体で楽しむこと。松茸が苦手であっても、しめじや舞茸など他の秋の味覚を通して季節を楽しむことは十分にできます。
「苦手」もまた、あなただけの秋の感じ方。その個性を受け入れて、自分らしい食の楽しみ方を見つけていきましょう。